 情報カード 情報カード
ありゃりゃりゃりゃもう3月になっちゃった。 そういえば、去年の12月、無寸草でのクリスマス展、来て下さったみなさま、どうもありがとうございました。おれは展示は滅多にやらないもんで、なんだか不安もありましたが、おかげさまで無事、楽しく終了することができました。いまごろお礼? こないだも書いたかと思うんだけど、去年からおれ、ノートも手帳も仕事の紙も、A4のルーズリーフに一元化するってことで生活を管理する方法を模索していましてね、けっこううまくいってて、やることなすことすごく効率良くなったはずなんだけど、いまごろお礼? いったい何ヶ月ぼやぼやしてんだか。 どこをどうすりゃもっと生活テキパキいけるんだろうね。これでも昔よりはずいぶんと行動的になったつもりなんだけどね。 昔のおれは、朝起きて、今日はお出かけするぞって思って準備しているうちに夕方になっちゃって、しょうがないから明日にしようって思ってさっさと布団に入って寝てしまう。なんてことよくあった。あのころにくらべたらなんという活動家であることか。 そうそう、去年はA4ルーズリーフ作戦のほかに、情報カードも生活に取り入れようと、なんだかんだと試行錯誤していたってこともこないだ書きましたっけね。 情報カードは、おれはいままで3回チャレンジしている。たしか梅棹ナントカさんっていう先生が書いた「知的生産の技術」っていう有名な本があってさ、その梅さん、日常のなんでもかんでもを情報カードで分類整理して、非常に効率のよい生活をなさってらっしゃるようなね、そんなような本をおれずいぶん昔に読んでさ、感化されちゃったわけさ。いつごろだっけな、たぶん前世紀、もしかしたら昭和の時代かな、忘れちゃったけど。 なもんなんだけど、情報カードってのは、なかなかうまく使いこなせないわけだ。まんがのキャラ設定とか、いろいろなアイデアをカードにメモしてカードボックスに分類整理すれば、なんだかすごいことができそうだぞっていう夢だけは大きくふくらむのだけど、そもそも部屋のかたづけだって適当なこんなぐーたら男が、バラバラのちいさい厚紙一枚いちまい分類整理ってアンタ、へそが茶を湧かすよ。 だけど、なんだかたまに使いたくなって、チャレンジしてしまうんだなあ情報カード。コンニャロウいつか使いこなせる日がくるかもしれないぞ、なんて思ってしまうわけだ。 去年はそんな3度目の正直で、情報カードについて、ネットでも調べたりして、様々な方法を模索してみた。それまでは梅さん推奨のちょっとおおきめな京大サイズを使ってみてたんだけど、今度はオーソドックスな大きさ、図書カードが原形の5×3サイズ。 ネットで調べてみつけた情報カードの使い方、ざっとこんな感じでしょうか。 ・梅棹さんの京大式 ・KJ法--カードを利用した論文の書き方。 ・PoIC--ひたすら時系列に整理してすべてを整理していく方法。 ・ヒップスターPDA--カードは適当にクリップに挟んで気らくに持ち歩いて身軽に生きるやりかた。 ・カードでTodo--方眼模様の情報カードのマス目を使ってマークシートみたいにこなした用事をチェックする。 そのほかに最近ジョッターっていうのが流行ってるみたいなんだけど、これは情報カードにメモを書くときに使う革製のかっちょいい下敷みたいなやつ。どうもどっかの有名な社長さんが愛用してらっしゃるのが御本で紹介されたみたいで、そこから流行っているような感じでしょうか、よくわかんないので違っていたらごめんなさい。 あとほかにもいろいろあったかな。まあ代表的なのはこんな感じ。 なんだかこういうの観てると、タメイキ出ちゃうんだよなあおれ。みんなすごいなあ、かっこいいなあ、おれもやりたいなあ。なんてさ。 でも実際カードを買って帰ってきて、机のうえにカードを広げてみると、うーん、さてどうしようって、毎回途方に暮れてしまう。これでどうしたらいいんだろう。なにを書いたらいいんだろう。これに対しておれはどうしたらいいわけ? 結局どうにもできなくて、去年もカード作戦断念したわけですな。2度あることは3度あると。 ま、そういうことでござんす。 ってことなんだけど、だけどね、これで終わりにしたら、せっかく買ったカードが勿体無いですよね。このまま捨てるには忍びない。こいつどうしたもんかって思うでしょ。早めに使い切る方法はなんかないもんか。さっさと終わりにしたいもんだなこのイライラカード、なんつってさ。 そしたら思いついたよ、Todo書いて壁に貼っちまおう。やることひとつにカード1枚。やることやったらビリビリやぶいて捨ててやる。コマ切れにしてゴミ箱だ。こりゃースッキリせいせいするに違いない。これでさっさとカードを処分して終わりにしてやろうってんで長らくほったらかしになってた机のまえのコルクボード、こいつに何年も貼りっぱなしになっていた、ホコリかぶってタバコのヤニとおてんとさんで黄ばんだチラシやハガキを片付けて、えいこんちくしょう、このくそったれなカードにやることやりたいことやらなきゃなんないこと一枚いちまい書いて並べて貼ってやったらこれがじぶんのなかでは大当たり。うひょーっ、こりゃ気分がいいじゃねえか、もしかしてこれが情報カードの正しい使いかたなんでねーの? なんて思うくらいにTodoカードとボード作戦が気に入ってしまった。 カードを早く処分するために始めてみたものなんだけど、こいつあいいやってんで、追加でまたカードたくさん買ってきちゃってさ、おまけにコルクボードももっと欲しい、なんて思っちゃって、近所のホームセンターで買い足した。まだまだ壁があまってるぞ、欲望のままに買い足したのが3枚、持ってたボードとあわせてぜんぶで4枚壁に並んじまいました。こりゃいいや。 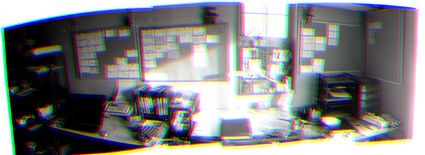 しかしよくよく考えてみたら、このやりかたっていろんなところで言われてますね。わりとオーソドックスなやりかたなのかな。 小説家が情報カードに書きたいエピソードを一枚いちまい書いてコルクボードに貼って、並びかえしながら構成を考えるなんていうのは有名なハナシとしてあって、小説の書き方なんかにもよく紹介されてそうだ。 むかしどこかの編集プロダクションかデザイン会社かに行ったときも、こういうボードにこんな感じにカードが並んで貼り出しているのを見たような記憶もある。どこだったかは思い出せないんだけど。 あと、アメリカのひとの書いたエッセイなんかに、「カードに書いて机のまえに貼っておく」っていうようなフレーズを何度か見たことがある。んー、おれの記憶にあるのでは、レイモンド・カーヴァーと、アニー・ディラード。ほかにも何人か見た記憶はある。 情報カードは日本よりもアメリカのほうが使ってるひと多いと思う。こんな几帳面なカードが、日本よりもアメリカのほうで流行ってるっていうのは、やっぱりカードはコルクボードに貼って使うものなんじゃないのだろうか? おれの偏見でいわせてもらえばアメリカ人は日本人より大雑把。几帳面に対する耐性はたぶんおれとどっこいどっこいなのが大多数なんじゃないの? 梅棹さんはカードは繰るものだとおっしゃってるけど、たしかに使い方はひとそれぞれ、どんな使い方でもいいんだろうけど、京大式もKJ法もPoicも敷き居が高すぎて、そこから入門してカードを使いこなすってのはちょっとたいへん。よほどマメなひとでないとできないんじゃないか? でもとりあえずやることなんかをなんでもかんでもカードに書いて貼ってみるっていうところから入るとすんなり使えるなんていうひとなら多そうな気がするような気がしないでもない気がする(ポストイットで同じことやってるひともネットで見ると多いようだけど)。 使っているうちに、写真左の2枚のボードがTodoが中心で、右の2枚が思いついたこととかいろいろ書いたカードを貼る感じに落ち着いてきた。最初は終わったら破り捨てるってことにしてたんだけど、だんだんカードに色をつけたり絵を入れたりするようになってきて、捨てるに惜しくなってきた。なんだか捨てられないのはルーズリーフに貼ってストックしてます。 カード初心者の試行錯誤のオハナシでした。 |